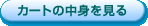- お香BOX
- チャクラストーン10種類完全セット
- 獣骨念珠MN1(白)
- 沈香粉普及品20g
- 獣骨念珠MGCチュプシ付き
- お守りケース入りビブーティ
- 伊勢神宮内宮<奉納塩>3点セット 【専用ケース・証明書・説明書付き】
- ミャンマー天然水晶
- ミャンマー天然水晶
- ミャンマー天然水晶
- ミャンマー天然水晶
- ミャンマー天然水晶
- カトラリー(スプーン、箸)
- ラオス仏像2902木彫(製作年不詳)
- 鬼夜叉護神ブレスレット
- 獣骨念珠BIG
- 白檀念珠
- 木製古代独鈷杵独鈷杵OLDBaj-S
- 木製古代独鈷杵独鈷杵OLDBaj-M
- ウッドカップA
- ビブーティ10gケース入り−6
- プラクルアン額装


-
ペンデュラム
■ヒマラヤ水晶マルカバスター型
■他、ヒマラヤ水晶ペンデュラム -
ストーンヘンジ
・ブレスレット・ネックレスヘッド
<英国正式認可品> -
オルガナイト
(生命エネルギー発生体)
・ペンデュラム
(ネックレス用革紐付) -
オルガナイト
(生命エネルギー発生体)・ピラミッド -
オルガナイト
(生命エネルギー発生体)・ワンド -
ヒーリングスティック・ワンド
■ヒマラヤ水晶、天然石で作られたヒーリングスティック - チャクラカラー・ワンドペンデュラム
-
五芒星・ペンタグラム
・ペンデュラム -
マジカル パワー
■五芒星・ペンタグラム -
チャクラストーン
10種類完全セット -
7(セブン)チャクラ
ネックレスヘッド - クリスタルチューナー、エンゼルチューナー
-
ルーンストーンセット
■ベルベット収納袋付き -
ルーンストーンセット
■天然ヒマラヤ水晶 - ダウジングL字ロッド
-
米国直輸入ホワイトセージ
■20g - ヒマラヤン・スマッジ・スティック
-
アーユルベーダ
(アーユルヴェーダ)
■スモーキングハーブ
Nirdosh(ニルドーシュ) -
サイババ
■ビブーティ
■ブレス、リング
■像 -
浄化、お香皿、香炉、燭台
■シェル
■素焼きお香皿
他 - 木製「すり鉢&すりこ木」セット
-
ヒマラヤ香木
■ヒマラヤ白檀
■ヒマラヤ柏槇
■アグール -
ネパールの樹脂香
(サルドゥープ) -
お香とお香BOX
HEM社
ナグチャンパ -
インド香木
■インド産白檀
パウダー、スティック -
ベトナム香木
■ベトナム産沈香(じんこう) - 樹脂香・ミルラ(没薬、もつやく)、乳香など
-
「神の木」パロサント
百楽香、本緑壇 -
チャコール
セージ、樹脂香などを焚く時に - プラスチックビーズネックレス
- ベネチアガラスビーズ
- ナガ族・アンティークガラスビーズ
-
鬼夜叉ブレスレット
・護神・金剛力士・仁王 -
マンモスの牙ブレスレット
・シベリアの凍土から発掘されたマンモスの牙使用 -
密林の魔除け数珠玉ブレスレット
Raja Kayu
帝王木数珠ブレスレット - 菩提樹とヒマラヤ水晶のブレスレット
-
白檀ブレスレット
インド・マイソール産 - 菩提樹、無患子(むくろじ)のビーズ
-
リシ(無患子)
ブレスレット - ルドラクシャ(蓮華菩提樹)ブレスレット
- 菩提樹ブレスレット
-
念珠、数珠
・菩提樹(ぼだいじゅ)
・白檀
・ルドラクシャ
・星月菩提樹 - 「聖獣」ヤクボーン、獣骨の念珠、数珠
- ガンジス川の水
-
ヒンズー、チベット仏教仏具
■シンギングボール
■金剛杵
■タルチョ、カタ、■お守り - チュプシ■念珠に付けるカウンター
-
チベット仏教デザインアクセサリー
・ネックレス・チョーカー
・梵字
・曼荼羅絵 -
ネパールチベットアジアデザインアクセサリー
■ネックレス、チョーカー
■バングル -
シルバーネックレスヘッド
■マニ車、ガウ
■ドルジェ、ブルバ
■ガネーシャ - チベット天珠(てんじゅ)
- チベット念珠
-
曼陀羅絵・たんか、仏画
■マントラ、カーラチャクラ
■ブッダライフ、他 -
曼陀羅絵、たんか絵、仏画
ポスター、ピクチャーカード -
ネパール、チベットバングル
■シルバーバングル
■銅、真鍮バングル
■チベットシルバーバングル -
西蔵(チベット)健康バングル
■薬用植物・釣藤鉤(ちょうとうこう)の枝のバングル - フリーチベットビーズブレスレット
- ボーンネックレス、リング
- 獣牙歯ネックレス
-
ストーンヘンジ
・ネックレストップ
・ブレスレット -
キリスト・十字架ネックレス
■キリストネックレス
■クロスネックレス -
伊勢神宮御神木
樹齢八百年神宮杉使用
■伊勢神宮ブレスレット -
伊勢神宮奉納塩
■陶器皿・陶器キャップ・奉納塩(約15g)
■専用ケース・証明書・説明書付き -
伝説の金属
■オリハルコン
■緋緋色金(ひひいろかね) -
プラクルアン
■神、仏、高僧、ご神木のお守り -
プラクルアン
■チベットから伝わった謎の神聖物質お守り - 玉(ぎょく)
-
ミャンマー水晶
・天然石 - レムリアン水晶、レコードキーパー、レーザー水晶
- 水晶原石
-
ヒマラヤ産出の原石
トルマリン
アクアマリン
ルビー
フローライト - ヒマラヤ産アクアマリンさざれ石(細石)
-
ヒマラヤ水晶ビーズ、ルース
■ファントム、ルチル - ヒマラヤ水晶さざれ(細石)
- ヒマラヤ水晶パウダー
- ヒマラヤ水晶座布団
-
ヒマラヤ天然水晶
■クラスター
■ポイント、他
■水入り水晶 - ヒマラヤ水晶球
-
水晶ネックレス
・クラスターネックレス
・ポイントネックレス
・勾玉、天珠ネックレス - ヒマラヤ水晶勾玉(まがたま)
- ヒマラヤ水晶マルカバスター
- ヒマラヤ水晶ガネーシャ
- ヒマラヤ水晶金剛杵(こんごうしょ)
- ヒマラヤ水晶手磨きピラミッド
-
ヒマラヤ水晶エレスチャル(骸骨)
ブレスレット - ヒマラヤ水晶ブレスレット
-
天然石ブレスレット
■ミャンマー翡翠ブレスレット -
コレクションケース付
シルバーリング -
シルバー925リング
・ネパール、チベットデザイン
・スカル - シルバーネックレス 天然石付き
- シルバーネックレス 石ナシ
- 天然石ネックレスヘッド
- ガラスアクセサリー
-
インテリア・雑貨
■民族工芸品
■木彫面
■木彫像
■仏像 - ラオス・仏像
- ラオス、不発弾アップサイクル商品
-
インテリア・雑貨
■銅製手作りやかん
■インド南京錠
■キャンドルスタンド
■他・雑貨 - ムエタイパンツ
- ネパールポンチョ
- 「サンスクリット・梵字」柄シャツ
-
ネパール手編みセーター
シェルパ - ファッション・小物
- バッグ、かばん
-
帽子
■ネパールシルク帽子
■トピー帽子、他 -
ネパール手すき紙ノート
■仏陀
■吉祥文様
■表紙・押し花デザイン
■絵手紙用 - 布、クロス
-
糸、紐、リサイクルシルク
■玉巻各種
■カセ巻徳用1000g他
■麻ひも、いらくさ -
ヒマラヤのはち蜜
ヒマラヤンハニー - ホッとする岩塩ランプ
- ヒマラヤ岩塩
- ソープナッツ(リタ)
-
手作り石鹸
■白檀石鹸
■水晶パウダー石鹸
■ヤクミルク石鹸 -
純銅(銅100%)メダル
■銅の殺菌効果をお手軽に -
ニーム(Neem)
■原木
■オイル
■パウダー -
天然バター、天然保湿回復剤
■コカムバター -
ハーブ入りアイマスク
アイピロー -
ヒマラヤ水晶スティック
マッサージスティック
- ■浄化・サウンドヒーリング
- ■浄化・香りヒーリング
- ■視覚ヒーリング
- ■ヒーリングパワーストーン
- ■ヒーリングパワーアクセサリー&オブジェ
- ■ミステリーパワー
- ■ボディーヒーリング
- ■雑貨、ファッション、素材、アクセサリー
- ■マジカルヒーリング
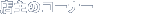

名前
伊藤千敏
メモ
合資会社 伊藤商事の運営するネットショップ、イトウ・ショウジの店長です。
こんなものはないか、あんなものが欲しい、というご希望がございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。